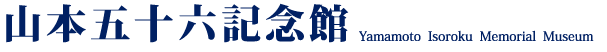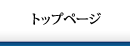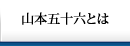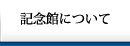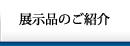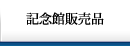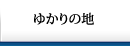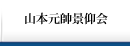見学あれこれ ~ しなやかかつ強い心で ~ (第17回 6/12更新)
(五十六さんは、どんな人だったのだろう?)を辿(たど)る
『明治~大正~昭和と、 ”激動の世紀をしなやかかつ強い心で生きた” 山本五十六』が皆様に伝わりますよう、こちらのページで少しずつ紹介していきたいと思います。お楽しみいただければ幸いです。
■第17回(2024/6/12記)
前回、ハーバード大学入学の報告をする「大正8年(1919)9月3日 高野季八宛」の書簡について紹介いたしましたが、五十六さんはその手紙に ”(前略)どうせ永くも一年、短かければ今年一杯にてワシントンへ参らねばならぬことと存じおり候につき(後略)” と、今後の見通しも書いています。
また、同年12月 海軍中佐に昇進した五十六さんは、「大正9年(1920)2月23日 西山伊豆子宛」の書簡で、アメリカ女性の自立した生活ぶりと、日本における新しい女性の生き方を諭しています。郷里長岡の友人 梛野 透(ナギノ トオル)の姪で当時14歳だった 伊豆子さんへ、やさしい言葉で、語りかけるように書いています。
“(前略)日本よりは早く自活の出来る仕組に社会がなって居りますから、女でも男でも力を惜しまず働けば、食っていくだけの事は出来ますのが日本よりは、たしかに進歩しておりますし、又それだから、国が発展して行く様に思はれます。日本もこの頃は、女の職業はましましたが、(中略)範囲が狭く、又、高等女学校卒業だけ位では、とても自分が独立して行くなどとは行きませんから、女はどうしても自由を束縛され易く、親も本人も早く身をかたづけることだけを考へ、(後略) “
100年以上も前に五十六さんが書いた手紙から、日本女性へのエールと五十六さんの慧眼(けいがん)が、存分に伝わってきます。
============⇒
(あぁそういえば、連続テレビ小説も近現代の女性達がテーマだなぁ)とか(あのオープニング曲いいよね~カラオケで歌ってみよう)などと思っている方、100年前の時代に注目ですよ~。それでは次の機会をこうご期待。
- 長岡市郊外 関原町にある新潟県立歴史博物館は、新潟県の歴史・民俗を総合的に紹介するとともに全国的・世界的視点から縄文文化を広く研究・紹介する博物館です。縄文時代や雪国の暮らしのエリアなど充実した常設展示のなか、近現代エリアでは、新潟の女性たちの働きぶりが人物模型で紹介されています。詳細はコチラ(公式ホームページ)
■第16回(2024/5/8記)
結婚の翌年 大正8年(1919)、五十六さんは米国駐在員として5月に渡米します。ボストンに下宿をとりハーバード大学の英語夏期講習に参加しつつ、夜は英会話の学習をしました。そして、9月の新学期からハーバード大学に入学し英語習得に励みました。
展示室の “世界をめぐる” のコーナーには、五十六さんが語学勉強のために購入した「シェイクスピア全集」や、ハーバード大学入学の報告をする「大正8年(1919)9月3日高野季八宛」の書簡があります。書簡には、大学での履修科目と意義などのほか末尾に ” 水饅頭が喰ひたいスケ買ふて呉らっしゃいスイー ” と長岡弁で書かれた文面を見ることができます。
============⇒
ここで、(ん~?水まんじゅう?)(葛菓子かな~??)なんて思った方がおありかもしれませんが、葛菓子ではありませんよ~。映画『聯合艦隊司令長官 山本五十六』(東映2011年12月全国劇場公開作品 /監修・原作:半藤一利 /特別協力:山本義正 /主演:役所広司)に、水まんじゅうを食べるシーンがでてきます! どんな食し方をしているか…チェックしてみてくださいね~。それでは次の機会をこうご期待。
■第15回(2024/3/21記)
結婚式がすんで11日目、新婦の禮子(レイコ)さんは、五十六さんの兄 季八(キハチ)夫婦に結婚式の礼状を書きました。 “ 此度は皆々様の御蔭を以って、万事滞りなく相済み申し候段、深く御礼申しあげ参らせ候 ” 展示されている「大正7年(1918)9月11日 高野季八、せい夫人宛 」の書簡からは、流麗で随所に力強さを感じさせる、才媛で謙虚な新婦 禮子さんの人柄がしのばれます。
そして壁面には、昭和16年(1941)正月撮影の写真「家族とともに」が展示されており、写真中央に禮子さん・その右肩下に五十六さん、他に長女の澄子さん・二男の忠夫さん・季八兄さんの長男 務さんや、禮子さんの妹の夫 斎藤正久 海軍大佐も写っています。
============⇒
ここで、(五十六さんも達筆だけど、禮子さんも字が上手なんだね~。)とか(上手に字が書けるようになりたいなあ。)などと思った方もおありかもしれませんが、先人の筆跡を訪ねる旅も面白いですよ。春の陽気にいざなわれ先人の筆跡訪ねに、誰かと一緒に出かけてみませんか?
■第14回(2024/2/8記)
展示室には、もう一点「結婚記念写真」が展示されています。こちらは「結婚記念写真(水交社)」の題名で、“大正7年(1918)8月31日の結婚式の際に撮影” の集合写真です。前列中央に新郎新婦、その両隣に仲人の海軍大佐 四竃 孝輔(シカマ コウスケ)夫妻と海軍少佐 堀 悌吉(ホリ テイキチ)夫妻が着座し、2列目には、五十六さんの兄:高野家五男 季八(キハチ)さん、 高野家長男 譲さんの子で五十六さんの姪:京(キョウ)さん も写っています。
仲人の四竈孝輔さんは、明治9年(1876)宮城県生まれの海軍兵学校第25期生です。日本海海戦を第2艦隊参謀としてむかえ、大正6年(1917)2月からは侍従武官を務めていました。五十六さんは、大正7年6月24付書簡(長岡市史双書No45『山本五十六の書簡』参照)で 侍従武官海軍大佐にて堀の先妻及後妻の媒介者たる人 と、兄に四竈さんを紹介しています。
また結婚記念写真の他に、媒酌人である四竈さんの「神前誓詞」も展示されています。以下、神前誓詞から一部ご紹介いたしましょう。 ” ~ 憂瀬に立つ事ありとも其苦を共に堪ひ忍ひ幸かる時ニ逢てハ共に其楽を同しくして常磐樹の変らぬ色の相思ふ心を據る事なく互に輔翼して家政を整理すへく誓ひ奉る ~ “
============⇒
ここで、(自分達も神前式だったなぁ~)とか(チャペルで誓った時は緊張したなぁ~)とか、はたまた(苦楽を共にする人って誰かなぁ?)などと思っている皆様! “相思う心” で、つながる方々との日々をどうぞ慈しんでくださいね~!! それでは次の機会をこうご期待。
- 長岡市史双書No45「山本五十六の書簡」(税込1,500円)には、兄 季八さん宛の手紙や絵葉書が計98点紹介されております。
- 長岡市史双書のシリーズは、長岡市歴史文書館で入手できます。詳細はコチラ(長岡市立図書館-歴史文書館のホームページ)
■第13回(2024/1/24記)
展示室の山本家系図の隣には、新郎新婦の睦まじい「結婚記念写真」が掛けられています。これは、大正7年(1918)8月31日に水交社で結婚式をあげた五十六さん(34歳)と新婦 禮子さん(22歳)の写真です。禮子さんは旧会津藩士族の三橋家 三女で、会津高等女学校卒業後、家業の酪農を手伝っていた方です。どんな困難や貧しさにも耐え、家庭を守ってくれる女性と見抜いての結婚でした。
また、婚約の前日に禮子さんへ書き送った「大正7年(1918)7月8日付書簡」も展示されています。一部分をご紹介します。 ” 御母上様より御許をも頂き候ことなれば以後は他人とは思はず種々申宣べく候に付、拙家当ならば何事も御遠慮無く御申聞有之度候。自分儀は御聞及の通、多年海上に人となり世事万端に甚だうとく、且公私厳別奉公一途こそ自分一生の主義に有之候へば一家の私事に就ては人一倍の御辛労をも相かけ可申、今より御依頼致置候。”
厳しくも優しい文面のこの手紙は、それからの禮子さんの日々をきっと励まし続けたことでしょう。
============⇒
さて、遠い昔に恋文を書いた経験をお持ちの皆様… その思い出は甘い?しょっぱい?それとも赤面もの…?! たまに記憶をたどってみてはいかがでしょう。そしてデジタル世代の皆様も、たまには大好きなあの人へ手紙を書き送ってみてはいかが? それでは次の機会をこうご期待。
- 販売品のご紹介「絵はがき(5枚綴 ミシン線入)」(税込600円)
5枚綴の内容 1=アメリカ合衆国駐在員時代の本人写真、2=五十六揮毫の書「国雖大好戦必亡…」、3=藤原銀次郎が五十六に贈った茶器「勝鬨」、4=アメリカ駐在武官時代に撮影のアメリカの子供たち、5=山本司令長官搭乗機左翼の写真 の5枚です。記念に保管するもよし旅先から誰かに便りするもよし。
受付脇のお土産コーナーで販売中です。皆様のご来館をお待ちしております!
■第12回(2023/11/30記)
今回は、“山本五十六となる” のコーナーにある壁面展示「山本家系図」をご紹介したいと思います。パネルの系図を見上げると最上部には “[山本家始祖] 義成 ” と名が書かれており、その脇に小さく “ 帯刀左衛門尉 三河牛久保生れ 今川氏家臣 駿河久能城主 三万五千石領有 ” と説明があります。次に連なるのは “ [長岡山本家祖] 成行 ” の名です。その脇にやはり小さく “ 帯刀左衛門尉 名 勘右衛門 永禄七年牧野成定に仕える。所領二千百石 ” と説明があります。続いて、長岡山本家2代目の説明には “ 山本勘右衛門成政 ” “ 祖父帯刀左衛門家督相続。高千百石家老職、組支配 元和四年長岡打入の御供。二代藩主忠成に勤仕。” と書かれており、以下各代の説明に 家老・家老・家老・・・と 家老の文字が並びます。長岡山本家6代目には “ 精義、勘右衛門義方 号山本老迂斎 ” の名があります。老迂齋は、江戸中期に第4代藩主牧野忠寿(タダカズ)から第9代忠精(タダキヨ)に至る六代の藩主に仕えた方で、五十六さんの先祖:高野家4代目の高野栄軒・5代目の余慶と関係も深く、当ページ:第4回(2023/02/20記)の記事にご紹介しておりますので興味のある方は併読してみてはいかがでしょう。
============⇒
ここで、(字が小さすぎて読めないっ!)(老眼でねぇ見えないからね~ 残念だなぁ… )と展示説明を読むことを諦めている方、諦めないで大丈夫です。館内では展示図録の販売もしておりますので、来館記念の購入もありですよ。ご自宅で再読はいかかでしょう。更に拡大ルーペを併用すれば見やすいです。次回は、山本家名跡を継承した五十六さんのお話をご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。
- 「山本五十六記念館展示図録」通販承ります。詳細はコチラ(別のページに移動します)
- 今夏オープンしたばかり!「米百俵プレイス ミライエ長岡」には長岡のあゆみを堪能できるオススメ空間があります!
→ オススメ空間その1.「互尊文庫」ミライエ長岡3階フロアにあり、郷土の偉人の関連図書やデジタルコンテンツをご覧いただけます。詳細はコチラ(公式ホームページ)
→ オススメ空間その2.「第四北越ミュージアム」ミライエ長岡6階フロアにあり、長岡のあゆみ・長岡地域の銀行の歴史・北越戊辰戦後の復興に尽力した三島億二郎・岸宇吉・ランプ会などについて知ることができます。詳細はコチラ(公式ホームページ)
■第11回(2023/10/30記)
大正3年(1914)12月 海軍大学校(甲種)の学生になり、在学中の大正5年(1916)9月20日に改姓届がだされ、五十六さんは32歳の時に山本姓となりました。
当館では、両親亡き後、親代わりとなって最も関わった兄 季八(キハチ)さんに宛てた「大正5年(1916)8月7日付書簡」を展示しております。この書簡で五十六さんは、山本家相続に伴う関係者の会合が延期になった と伝えています。
このほか、室内には山本家系図や山本帯刀(タテワキ)作ひょうたんも展示しております。ひょうたんが入っていた箱も展示され、五十六さんの父 貞吉(サダヨシ)の兄の子で従兄弟にあたる田中浪江(ナミエ)氏が箱ふたの裏側に、その由来を筆記しています。
山本帯刀義路(タテワキヨシミチ)は北越戊辰戦争で西軍に捕らえられ、慶応4年=明治元年9月9日 会津飯寺(ニイデラ)に没します。そして明治21年、長岡城址に旧長岡藩家老の山本帯刀義路を偲ぶ石碑「舊(キュウ)長岡藩山本君碑」が建てられました。石碑は後に、長岡市東山連峰のふもとに位置する悠久山公園に移され現代に至っております。
============⇒
ここで、(山本帯刀義路って幕末から戊辰戦争の頃の人なのか)とか(飯寺って会津若松城から近いのかな?河井継之助記念館は只見町にもあるんだね)などと思っている方、河井継之助や戊辰戦跡を巡る旅もおすすめです。この続きは次回ご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。
- 悠久山公園内の23の石碑・史跡の散策はいかがですか!「悠久山で歴史巡り」はコチラ(長岡市ホームページ)
- 長岡市「河井継之助記念館(ツギノスケキネンカン)」はコチラ(公式ホームページ)※毎週火曜日と年末年始は休業します。
- 長岡市「北越戊辰戦争伝承館」はコチラ(長岡市ホームページ)※毎週月・金曜日と12/1~翌年3/31は休業します。
- 「只見町河井継之助記念館(ツグノスケキネンカン)」はコチラ(会津ただみ振興公社ホームページ)※令和5年は12/3(日)まで営業の予定。天候により臨時休館があるので状況は随時ご確認ください。
■第10回(2023/09/20記)
当館出入り口(風除室)の壁面には、長岡花火のポスターや他館の企画展告知ポスターなどが掲示されておりますが、五十六さん揮毫の書のポスターも掲示しています。一枚は河井継之助(カワイツギノスケ)の座右の銘を縦書きしたもの、もう一枚は横書きの四文字「心如鐵石」(心は鉄石の如し)です。
この「心如鐵石」(心は鉄石の如し)、展示室には縦書きで、五十六さんの父 高野 貞吉(タカノ サダヨシ)の書を紹介しております。 “心如鐵石 維時明治四十三年一月 為吉田君 八十二歳古道墨” とあり、明治43年(1910)1月、貞吉82歳の時に書かれたものです。 “鉄や石のように堅固な精神、どんな障害にも へこたれない強い心を持て” という教えが込められたものです。貞吉はこの3年後、大正2年(1913)2月に老衰で亡くなり、看病していた妻の峯も、半年後の8月に肺炎で亡くなりました。
五十六さん30歳の頃の「大正3年(1914)12月19日付渡部與宛書簡」では、” ~ 八月二十七日 間もなく逝去致し候次第、両親共に遂に死目にも会へず、葬式にも列せず、武門の常、父の遺訓として敢て残念とも存じ申さず候へども、今両三年と思ふ ふしもこれあり。~ “ と、(もう2、3年生きてて欲しかった…)と母 峯への思いを書き送っています。
============⇒
ここで、(故郷の親に会ってないなぁ、よしっ!今度の休みに会いに行ってこよう!!)、はたまた(山本姓になる話はまだなんか~い!!)と、思っている方もおいでかもしれませんが、この続きは次回ご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。
- ~祭りのご案内~「米百俵まつり」~ときを超え一日限りの長岡藩~ で時代行列・米百俵劇を楽しみませんか! 令和5年(2023)は 10月7日(土)開催です。 詳細はコチラ(長岡市ホームページ)
■第9回(2023/08/24記)
日本海海戦での重傷・療養から復帰した五十六さんは、明治39年(1906)2月巡洋艦「須磨」乗組をはじめ次々と海上勤務を経験します。訪問先からは、各地の特色などを短文にしたためた絵葉書を季八(キハチ)兄さん等に送っています。当館展示室「世界をめぐる」のコーナーには季八兄さん宛の絵葉書13葉が展示されており、巡洋艦「阿蘇」・練習艦「宗谷」乗組時に送った絵葉書 ①明治41年12月※(上海) ②明治42年4月※(ロサンゼルス) ③明治42年5月※(サンフランシスコ) ④明治42年5月※(バンクーバー) ⑤明治42年6月※(シアトル) ⑥明治43年5月(メルボルン) ⑦明治43年6月(シンガポール)の絵柄7葉がご覧いただけます。
上記絵葉書のうち、※印の文面は長岡市史双書No.45「山本五十六の書簡」に紹介されていますので、見学の際に見本誌参照・購入(税込1,500円)もおすすめです。
五十六さんは海軍兵学校卒業生の遠洋航海指導で、明治42年(1909)3月には北米へ向かい、同年10月に「宗谷」分隊長心得を経て海軍大尉・「宗谷」分隊長となりました。明治43年(1910)2月からの遠洋航海指導では、宗谷艦長:鈴木貫太郎の薫陶のもと、東南アジア・オーストラリアなどをめぐりました。
20代半ばを迎えた五十六さんの航海は、各地の風土や住む人々の熱気を直接感じることができる、日々発見に満ちたものであったことでしょう。
============⇒
ここで、(あれ? 山本姓になる話はいつするのかな??)と思っている方がおいでかもしれませんが、この続きは次回ご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。
■第8回(2023/07/14記)
五十六さんが季八兄さんに宛てた手紙に “(一人の友を得)候” と記した人物は、堀悌吉(テイキチ)です。堀さんは明治16年(1883)8月16日 大分県に生まれ、五十六さんと共に海軍兵学校第32期生として学校生活を送ります。明治37年(1904)11月、兵学校を卒業した二人は少尉候補生となります。卒業時は日露戦争の最中で、明治37年(1905)1月 堀さんは戦艦「三笠」に、五十六さんは巡洋艦「日進」に乗組を命じられました。堀さんは、同年5月27・28日の日本海海戦の様子を昭和21年(1946)5月成稿の手記で回想しています。
当館展示室の傍らでは “ 昭和18年12月8日 平田陽光 謹作「山本元帥像」” を展示しております。第2種軍装に白手袋姿の五十六さんが軍刀を携え敬礼する姿の人形です。その左手の人指し指・中指の傷痕は、五十六さんが21歳の時の日本海海戦で重傷を負い切断を余儀なくされた痕です。
そして展示室正面奥には、第一号として五十六さんに贈られた ” 軍人傷痍記章 “ が展示されています。五十六さんが54歳の時に贈られたものです。記章箱の底には “ 昭和13年9月30日下附 海軍次官 山本五十六 ” と自署されており、傷痍記章をどの勲章よりも大切にして喜んでいたことでしょう。
日本海海戦で受けた傷による障害を乗り越えてきた、五十六さんの誇りや様々な心情に思いを寄せて展示品の数々を見たとき、皆様はどのようにお感じになるでしょうか・・・。
============⇒
ここで、(21歳のころは高野姓だけど山本姓に改姓したのはなぜだったの?いつから? )と思う方もおいでかもしれませんが、この続きは次回ご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。
■第7回(2023/06/15記)
合格者200名中 2番、これは五十六の海軍兵学校入学試験での成績です。五十六の兄:季八(キハチ)は、すべてが試験成績で評価される海軍兵学校で懸命に勉強する弟の健康を心配しました。五十六は兄に宛てて「明治36年(1903)9月23日付書簡」に “ ご心配のほど誠に申し訳これなく万謝奉り候 ” と書いています。 書簡の内容を少々ご紹介しましょう。
兵学校受験前の勉強の様子を ” とても身の如きをもて入学せられむとは 思いもせず、又強て のぞみも致さず候へき。しかし まじめに七月に至るまで五月より高橋※ の階上にて勉強 ” (※高橋=五十六の姉:加壽(カズ)の嫁ぎ先) と綴っています。 また、試験初日の試験の出来栄え・受験後の合否を待つ心境・入学後の試験勉強の様子・早逝した級友や甥の力(チカラ)のこと・一人の友を得たこと等々、当時19歳の五十六さんの感じていたことが具体的に書かれています。
当館受付脇に設けられた販売コーナーで、この手紙を紹介した図書を購入することができます。山本五十六記念館展示図録(税込1,100円)・長岡市史双書No.45「山本五十六の書簡」(税込1,500円)で、ご帰宅後にゆっくり再読はいかがでしょうか。
============⇒
ここで (おぉぉ? “一人の友を得候 ” …って誰よ?) と思った方もおいでかもしれませんが、この続きは次回ご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。
【追記】長岡の歴史に関する刊行物 “長岡市史双書” は、長岡市立中央図書館文書資料室が発行しております。平成10年4月に長岡市史編さん室の業務と所蔵資料などを引き継いだ資料室は只今移転作業に伴い休館しておりますが、令和5年7月1日に長岡市歴史文書館としてリニューアルオープンします!! 長岡市の古文書や行政資料を公開しているほか、県内の歴史関係の文献を備えており、郷土の歴史について知りたいことや研究したいことを調べることができます。オープン準備の状況は文書資料室ホームページや同サイト内 “職員のつぶやき” からもご覧になれます。7月のリニューアルオープンが楽しみですね。
- 「長岡市歴史文書館」についてはコチラ(長岡市立中央図書館文書資料室ホームページ)
■第6回(2023/05/25記)
五十六さんは明治23年(1890)4月、阪之上尋常小学校へ入学します。明治2年(1869)に創設された国漢学校と米百俵の精神を受け継いだ小学校で、1年生の時の担任は渡部與(ワタベアタヘ)先生でした。渡部先生との交流はこの時からずっと続いていきます。
当館内では、海軍大学校時代に渡部先生に宛てた「大正3年12月19日付書簡」「大正4年4月15日付書簡」のほか、連合艦隊司令長官時代に先生のご家族に宛てた「昭和15年6月20日付書簡」をご覧になれます。
明治29年(1896)3月に小学校を卒業した五十六さんは、明治5年(1872)開学の長岡洋学校を前身とする長岡中学校に「長岡社」の奨学金を受けながら通います。長岡社は明治8年(1875)に小林雄七郎らの提唱によって設立された育英団体です。
展示室のショーケース内には、五十六さんが中学校時代に使用した勉学ノート「不乱苦林」と、英文の小冊子「フランクリン自叙傳」(ジジョデン)が展示されています。ベンジャミン・フランクリン(1706年-1790年)は実業家や科学者としての功績のほか、アメリカの独立運動を指導した政治家としても有名です。展示されている勉学ノート表紙には、“ 不乱苦林 ” ” 明治卅四年正月 “ ※明治34年(1901) などの文字が墨で書かれています。 その年の3月に中学校を卒業する五十六さんの心が伝わってくるようです。
============⇒
ここで(5月も半ばだな、五十六さんのように猛勉強しよう!)と張り切っている方もいらっしゃるかもしれませんが、この続きは次回ご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。
■第5回(2023/03/08記)
第5回は、五十六さんの家族についてご紹介いたします。戊辰戦争後の明治17年(1884)4月4日、五十六さんは父 高野貞吉(タカノサダヨシ)と母 峯(ミネ)の六男として玉蔵院町(現在 阪之上町3丁目)で生まれました。展示室では、実際の生家の写真「玉蔵院町(阪之上町三)の生家」がご覧になれます。
高野家の兄弟は8人(うち一人は早世)で譲(ユズル)を筆頭に、登・丈三・惣吉・加壽(カズ)・季八(キハチ)と続き、五十六さんは末子です。明治維新後、長兄の譲は北海道で樺戸監獄の看守長を務めており、譲の子供たちは高野家に預けられていました。展示室の生家写真の左隣りには、8歳の頃の五十六「最初の写真」があります。明治25年(1892)4月、当時13歳だった兄 季八(キハチ)が東京の歯医者へ修行に行く前に他家へ嫁いだ姉の加壽がお金を出し、譲の長男 ※五十六の甥 力(チカラ) ・季八・五十六と一緒に写した、記念写真です。この写真から5年後の明治30年(1897)9月、五十六さんが長岡中学2年生の時、甥の力は22歳で病没しました。力が没して6年後、海軍兵学校へすすんだ五十六は兄 季八宛書簡のなかで、力 や故郷を懐かしんでいます。
============⇒
ここで(4月4日!誕生日一緒だ!)とか(小中学校時代の五十六さんはどんな少年だった?)などと興味津々の方がいらっしゃるかもしれませんが、この続きは次回ご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。
■第4回(2023/02/20記)
第4回は、藩学と山本家・高野家祖先についてご紹介します。長岡藩9代藩主 牧野忠精(タダキヨ)(在任期間1766~1831)の時代、文化5年(1808)に学問所「崇徳館(スウトクカン)」が創立しました。忠精は、京都所司代の頃に古義派の儒学者 伊藤東所(トウショ)に教えを請いました。のちに東所の子 伊藤東岸(トウガン)は、長岡に招聘され文化12年(1815)崇徳館都講を命ぜられます。
古義学は、孔子・孟子の教えの根源を探究しようとする江戸時代の儒学の一派です。忠精を含め藩主6代に仕えた家老 山本老迂齋(ロウウサイ)は、朱子学を修めたのち古義学に入り、自邸内に書堂を設け研修奨励しました。そして、藩主7代に仕え山本老迂齋の信任厚かった高野家4代 高野栄軒(タカノエイケン)も、京都の伊藤東所に書を寄せ疑義を質し古義学に傾倒しました。高野栄軒は、山本老迂斎 の命を受け牧野家 家譜の編修、藩内の学問の興隆に力を尽くしました。その子 余慶(ヨケイ)もまた古義学を学び、伊藤東所とも交流を深め、藩主 忠精とその弟 忠義の侍読として学問の教授と進行に当たりました。
当館では、「高野余慶の著作物」:粒々辛苦録 (リュウリュウシンクロク)』 乾(ケン)・坤(コン)の2冊のほか、伊藤東所撰文の「高野家の祖先、高野栄軒の碑」のパネル展示がご覧になれます。
============⇒
ここで(うーん、 そろそろ五十六少年のことが知りたい!)と思った方がいらっしゃるかもしれませんが、この続きは次回ご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。
■第3回(2023/01/24記)
第3回は、高野家と長岡藩のルーツについて紹介します。展示室の「年譜」の隣りには『高野五十六の誕生』のコーナーがあります。壁面には「高野家系図」が掲示されていて系図の最上段を見ると・・・ 三河に出生 真田伊豆守家中:宇津七郎左衛門 の 弟の 高野七郎左衛門 が、慶安元年(1648)に牧野家に召し出され、初代長岡藩主 牧野忠成 に仕えた ことが分かります。長岡藩士族 高野家 の始まりです!
なお、長岡藩祖の “牧野忠成” は天正9年(1581)三河国牛久保(現在の愛知県豊川市)に生まれました。徳川家康・秀忠に厚遇された忠成の ”忠” の一字は、徳川秀忠の一字を授けられたものです。慶長5年(1600)の関ケ原の戦いでは徳川秀忠に付き出征、慶長19年(1614)の大阪冬の陣・翌年(1615)の大阪夏の陣に参戦し武功を挙げました。そして元和4年(1618)、忠成は長岡藩主(在任期間1618~1655年)となりました。
牧野忠成が長岡藩祖となってから十二代 忠訓まで 長岡藩 牧野家 は続き、長岡藩士族 高野家 は儒学者の家柄として藩主に代々仕えていきます。
============⇒
ここで(ふ~ん、儒学者の家系? どんな仕事をしてたの?)と興味を持った方がいらっしゃるかもしれませんが、この続きは次回ご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。
- 戦国武将 長岡藩初代藩主 ”牧野忠成” の特集はコチラ(長岡市ホームページ)
- 長岡藩主の資料館「長岡藩主 牧野家資料館」はコチラ(公式ホームページ)
- 長岡の歴史を紹介している「長岡市郷土資料館」はコチラ(長岡市ホームページ)
■第2回(2023/01/11記)
新年を迎え、皆様どのような毎日をお過ごしでしょうか。よい一年となりますよう、関係者・スタッフ一同ご祈念しております。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
第2回は、五十六さんの誕生について紹介いたしましょう。正面壁面ガラス内の”肖像画”と”直筆書簡”の展示を見学後、壁面裏側に移動すると「年譜」が掛けられております。 ”山本五十六のあゆみ~西暦/年号~日本と世界の動き” が簡単にざっくりと、パネルで紹介しています。(五十六さんの年齢は記載されておりませんので頭の体操がてら、生まれた年・西暦1884年を基準に ”暗算” で、年齢を算出してみましょう!)
幕末・戊辰戦争後に元号は「慶応」から「明治」へ変わり、明治17年(1884)4月4日、五十六さんは高野貞吉(タカノサダヨシ)の六男として生まれました。高野家は三河武士を遠祖とし、江戸時代の長岡藩で儒学者として地歩を固めました。祖父・父 ・兄2人は戊辰戦争に参戦、祖父は戦死・高野家も全焼し、戦後再建された木羽葺の小さな家が、五十六さんの生家でした。当館では「玉蔵院町(坂之上町三)の生家」写真をパネルで展示しております。生家・高野家は昭和20年(1945)8月1日の長岡空襲で焼失した後、山本記念公園(昭和33年竣工)内に復元され、今に伝わっております。
============⇒
ここで(ん、三河武士…?長岡藩…? どういう繋がりが??)と思われた方がいらっしゃるかもしれませんが、この続きは次回ご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。
- お出掛け情報1 長岡の歴史を紹介している「長岡市郷土資料館」はコチラ(長岡市ホームページ)
- お出掛け情報2 長岡藩主の資料館「長岡藩主 牧野家資料館」はコチラ(公式ホームページ)
- お出掛け情報2-1 牧野家資料館別階フロアの「長岡市立科学博物館」はコチラ(公式ホームページ)
- お出掛け情報3 越後長岡藩 幕末ミュージアム「河井継之助記念館」はコチラ(公式ホームページ)
- お出掛け情報4 長岡空襲(昭和20年8月1日)を語り継ぐ「長岡戦災資料館」はコチラ(長岡市ホームページ)
- お出掛け情報5 山本記念公園についてはコチラ(新潟観光ナビ 公式ホームページ)
■第1回(2022/12/23記)
まず、入館受付をすませた先 正面 壁面ガラスの内には「山本五十六肖像画」が掛けられております。この絵は五十六さんが亡くなった後に描かれたもので、山本五十六記念館展示図録(館内受付で販売中)の表紙にも使われております。
そして、肖像画の下部には、五十六さんが長岡中学校生徒時代に兄 高野季八に宛てて書いた直筆書簡を展示しています。明治32年8月14日付の書簡で、友人達と旅をしたエピソードが書かれています。達筆で的確な表現に圧倒される書簡です。柏崎北条~田尻~番神~米山登山~鉢崎~荒浜~椎谷~尼瀬~出雲崎市街~ ・・・ 新潟県中越地方に馴染みのある地名が書かれています。
============⇒
ここで(ん、兄 高野季八…タカノ?山本五十六…? 名字が違うナゼ??)と思われた方がいらっしゃるかもしれませんが、五十六さんの誕生については次回ご紹介いたします。それでは次の機会をこうご期待。